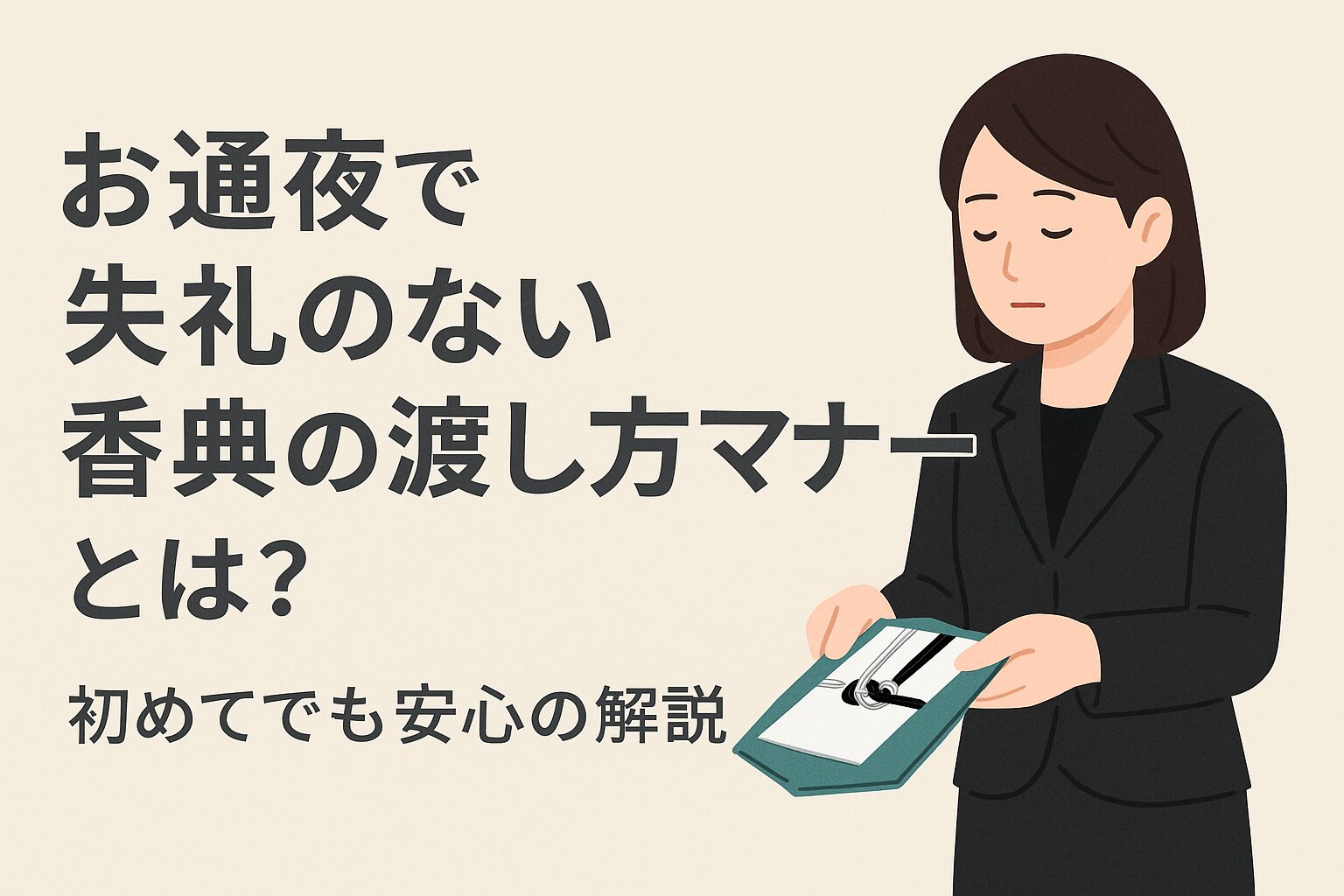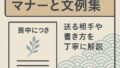お通夜に参列することになったけれど、「香典っていつ、どうやって渡せばいいの?」「ふくさの使い方がわからない…」と悩んでいませんか?
初めての場では誰もが戸惑うものです。失礼のない振る舞いをしたいけれど、細かなマナーは意外と知られていません。
この記事では、お通夜での香典の渡し方マナーを、初心者の方にもわかりやすく解説します。言葉遣いや受付の有無による違いなど、実際の場面で役立つ情報を丁寧にご紹介。これを読めば、不安なくお通夜に参列できます。
香典を渡すタイミング
受付がある場合
お通夜では、受付で香典を渡すのが一般的なマナーです。到着したらまず受付に進み、芳名帳(記帳台)で自分の名前を丁寧に記入しましょう。その後、ふくさから香典袋を取り出して渡します。
このときのポイントは以下の通りです。
-
香典袋は表書きが相手から読める向きで差し出す
-
ふくさの上に香典袋を乗せたままでもOK(手渡ししやすければ袋だけでも可)
-
相手がご遺族でなくとも、深く一礼し「このたびはご愁傷さまでございます」と一言添える
また、受付の列が混雑している場合でも、焦らず丁寧な動作を心がけましょう。香典を投げ出すように渡したり、無言で差し出すのはマナー違反とされるため注意が必要です。
※なお、香典袋はあらかじめふくさの中に入れて持参し、受付の直前で取り出すようにするとスムーズです。鞄の中をゴソゴソ探すような仕草は避けましょう。
受付がない場合
まれに、お通夜会場に受付が設けられていない場合もあります。たとえば小規模な通夜や、家族葬形式の場面などでは、参列者がそのまま会場に通されることがあります。
このようなとき、その場で勝手に香典を渡してしまうのは控えた方がよいでしょう。適切な相手やタイミングを見極めるため、以下の対応がおすすめです。
-
会場のスタッフ(葬儀社)や係員に確認する
例:「香典をお渡ししたいのですが、どなたにお願いすればよろしいでしょうか?」 -
案内があるまで自席で待機する
式が始まる前に喪主や親族から案内されることもあるため、落ち着いて待つ姿勢も大切です。
場合によっては、式後やお焼香のタイミングで案内されることもあります。無理に自分から動かず、会場の流れに合わせるのが無難です。
このように、状況によって香典を渡すタイミングや相手が変わるため、焦らず、確認を取りながら丁寧に行動することが大切です。マナーを守りつつ、遺族の心情にも配慮した対応を心がけましょう。
香典の正しい手渡し方
香典の向き・差し出し方
香典を手渡す際は、表書き(「御霊前」などの文字)が相手から読める向きに持つのがマナーです。香典袋の上辺(封筒の開け口)が自分側になるようにし、両手でそっと持ちましょう。
受付では、以下の手順で渡すのが丁寧な所作です。
-
記帳を終えたあと、静かに一歩進みます
-
一礼または軽く会釈をして、「このたびはご愁傷さまでございます」と一言添えます
-
表書きの向きを確認し、両手で丁寧に香典袋を差し出します
このとき、片手で渡す、無言で差し出す、慌てた手つきになるなどは避けましょう。香典は「気持ちを形にしたもの」ですので、その扱い方にも心を込めることが大切です。
また、受付にテーブルがある場合は、テーブルの上で一度香典袋を整えてから差し出すと、より丁寧な印象を与えます。
ふくさの扱い方
香典袋は、ふくさに包んで持参するのが正式なマナーです。ふくさには「汚れや折れから香典を守る」という意味があり、マナーとしても実用面でも大切なアイテムです。
色の選び方には注意が必要で、弔事には以下のような寒色系の落ち着いた色が適しています。
-
紺色
-
グレー
-
紫(慶弔どちらにも使える万能色)
赤やピンクなどの明るい色、柄が派手なものは避けましょう。
香典を渡すまでの流れは以下のようになります。
-
会場に着く前に、香典袋をふくさに包んでおく
-
受付に進む直前で、静かにふくさを開く
-
香典袋を取り出し、表書きの向きを確認
-
ふくさの上やテーブル上で香典袋を整えてから渡す
ふくさを広げたまま香典袋をその上に乗せて差し出してもよいですし、袋だけを渡しても問題ありません。どちらの場合も、丁寧な所作と一礼が添えられていれば十分に礼儀を尽くした対応になります。
このように、香典の手渡しは形式だけでなく、気持ちや心配りを込めることが何より大切です。事前に動作を確認しておけば、当日も落ち着いて行動できるでしょう。
言葉遣いマナー
「このたびはご愁傷さまです」の使い方
お通夜の場では、香典を渡す際やご遺族に挨拶をする際に、「このたびはご愁傷さまでございます」という言葉を用いるのが一般的です。
これは最も丁寧な表現のひとつであり、形式としても感情としても適切な言い回しです。
使用する際のポイントは以下の通りです。
-
深く一礼を添える
-
声は小さめに、落ち着いたトーンで話す
-
悲しみを共有する気持ちを込めて丁寧に
また、相手との距離感や関係性によっては、次のような言い回しも使われます。
-
「心よりお悔やみ申し上げます」
-
「突然のことで、驚いております」
-
「ご家族の皆さまもどうかお体にお気をつけください」
ただし、冗長にならないよう、簡潔で慎み深い言葉を選ぶのがマナーです。
言ってはいけない言葉
お通夜の場では、何気ない一言が相手の心を傷つけたり、不快な印象を与えることがあります。以下のような言葉は避けるようにしましょう。
-
「頑張ってください」
励ましのつもりでも、喪失直後のご遺族には負担となる可能性があります。精神的につらい状況に「努力」や「元気」を求める言葉は控えましょう。 -
「また会いましょう」
日常会話では自然な表現でも、「再び」という言葉は「不幸の繰り返し」を連想させ、忌み言葉(いみことば)とされることがあります。 -
「お疲れさまでした」
弔問後に軽く言いがちですが、亡くなった方に向けたように受け取られると、失礼にあたることも。代わりに「お世話になりました」などを使うのが無難です。 -
「亡くなってよかったですね」などの不用意な感想
たとえ病気が長引いていたとしても、第三者が安易に「楽になった」などと話すのは不適切です。
また、「重ね重ね」や「度々」「再び」など、繰り返しを意味する言葉も避けるべき表現とされています。これは、不幸が繰り返されることを連想させるため、弔事では「忌み言葉」としてタブーとされているのです。
このように、言葉選び一つで弔意の伝わり方は大きく変わります。形式的なフレーズでも、丁寧な所作と気遣いが伴えば、それだけでご遺族の心に寄り添う姿勢が伝わるはずです。緊張してしまっても構いません。大切なのは、相手を思いやる気持ちを込めることです。
受付がない場合の対処法
喪主への直接手渡し
まれに、お通夜や家族葬などで受付が設けられていない場合があります。受付がないからといって香典を渡さないのは失礼にあたることもあるため、適切な方法で対応する必要があります。
そのような場合には、式が終わった後や焼香が終わったタイミングを見計らって、ご遺族(主に喪主)に直接香典をお渡しするのが望ましい対応です。
渡す際には、以下のような言葉を添えると丁寧です。
-
「突然お渡しして申し訳ありません。ご霊前にお供えください」
-
「ご無礼をお許しください。心ばかりですがお納めください」
ポイントは、騒がしくならないように控えめな声で丁寧に、かつタイミングに注意することです。
避けるべきタイミングや配慮点:
-
式の最中や読経中は渡さない
-
焼香の順番を乱さない
-
会場のスタッフや遺族の負担にならないよう、静かに振る舞う
可能であれば、式後にスタッフへ「香典をお渡ししたいのですが、ご遺族に直接お渡ししてもよいタイミングを教えていただけますか」と声をかけると、よりスムーズです。
郵送する場合のマナー
やむを得ず参列できない場合や、受付や手渡しの機会がない場合は、香典を郵送で送ることも可能です。ただし、現金を扱うため、適切な方法で送ることが大切です。
郵送の手順とマナー
-
現金書留を使う
香典を郵送する際は、必ず「現金書留」を利用しましょう。普通郵便やレターパックでは現金を送ることができません。 -
香典袋に入れ、ふくさで包む
香典袋には中袋(中包み)も含め、金額や氏名を正しく記入します。そのうえで、ふくさや包み紙に包んで、丁寧に封筒へ入れます。 -
お悔やみの手紙を同封する
香典だけを送るのではなく、必ず一筆添えましょう。文面は堅苦しすぎず、心のこもった内容を意識すると良い印象を与えます。
手紙の例文(一文):
「心ばかりのものではございますが、ご霊前にお供えいただければ幸いです。」
-
送り先の確認を忘れずに
喪主の自宅か、葬儀会場の受付宛かなど、送り先の住所と名前は正確に記載しましょう。葬儀社に確認しても丁寧です。
このように、受付がない場合でも、ご遺族の負担にならない方法で、誠意をもって香典を届けることが大切です。対面でも郵送でも、気持ちとマナーをきちんと伝えることで、遺族に失礼のない対応ができます。
まとめ|失礼のない香典の渡し方
お通夜での香典の渡し方は、相手への気遣いや礼儀が試される場面でもあります。以下のポイントを押さえておきましょう。
-
基本は受付で渡すが、状況に応じて柔軟に対応
-
香典袋の向きやふくさの扱いに注意
-
言葉遣いは慎ましく、丁寧に
-
郵送や直接手渡しの場面でもマナーを守る
正しい香典の渡し方を知っておくことで、故人や遺族に対して誠意をもって弔意を伝えることができます。