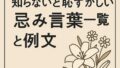「ママ、お葬式ってどうやってお辞儀するの?」
先日、義母のお通夜で、祭壇の前でのお辞儀に戸惑いました。今まで何となく周りの真似をしてきたけど、本当にこれでいいのかな…と。
葬儀の場では、遺族にも参列者にも失礼がないようにしたいですよね。今回は、仏式・神式・キリスト教式それぞれの祭壇の違いや、お辞儀の作法、線香や焼香のポイントまで、私自身の体験も交えてお伝えします。これを読めば、いざというとき落ち着いて振る舞えますよ。
祭壇とは何か?
葬儀における祭壇の役割
葬儀場に入ると、一番奥に立派に飾られた祭壇がありますよね。
初めて参列したとき、私は入口で受付を済ませて席に座り、正面を見た瞬間、「このお花がいっぱい飾られている場所って、何だろう…」と素朴に疑問に思ったのを覚えています。
祭壇とは、亡くなった方(故人)を祀るために設けられる特別な場所です。
中央には遺影や位牌が置かれ、その周りを生花や供物、宗教ごとの道具で美しく飾ります。見た目の華やかさだけでなく、そこには故人への敬意や感謝の気持ちが込められているんですね。
お通夜や告別式では、この祭壇に向かってお辞儀をしたりお焼香をあげたりします。つまり、参列者が故人に最後のご挨拶をする「祈りと別れの場」。
仏式・神式・キリスト教式の違い
葬儀には大きく分けて仏式、神式、キリスト教式があります。それぞれの宗教観によって、祭壇の作りやお参りの方法も変わってくるんです。
仏式
日本で最も多い葬儀形式で、祭壇中央には遺影や位牌が置かれ、その前に仏具や供物、たくさんのお花が飾られます。お線香や焼香で香を供えることで、故人の冥福を祈るのが基本。
私の祖父も仏式でしたが、お線香をあげたときに「これで最後のお別れなんだ」と実感して、涙が止まりませんでした。
神式
神道の葬儀は「神前祭」と呼ばれ、仏式と違って白木で作られた祭壇に榊(さかき)や玉串が供えられます。
お線香や焼香はなく、代わりに玉串奉奠(たまぐしほうてん)という儀式を行うのが特徴です。
以前、友人のお父さんのお葬式が神式で、「あれ?お線香あげないの?」と驚きました。玉串奉奠のやり方も初めてで、前の人の動作を必死で見て真似したのを覚えています。
キリスト教式
キリスト教式では、カトリックの場合は十字架や聖母マリア像、プロテスタントでは十字架のみが祭壇に飾られます。
焼香や玉串の代わりに献花を行うことが一般的です。
近所の方の葬儀がキリスト教式だったとき、白いカーネーションを手渡され、祭壇の前で静かにお花を置きました。お線香や焼香と違って、花の香りと優しい雰囲気に包まれていて、「こんな葬儀もあるんだな」と感じた記憶があります。
私も祖父の告別式が仏式、友人のお父さんが神式、近所の方がキリスト教式と、短期間で立て続けに参列したことがあり、そのたびに「今回はどんな作法なんだろう」とドキドキしていました。
でも、こうして違いを知っておくと、いざというとき慌てず落ち着いて行動できます。周りの人に「ちゃんと知ってるね」と思われると、自分自身も少しだけ自信が持てますよ。
お辞儀の作法
二礼一拍手一礼は仏式ではNG?
「神社でやるお辞儀みたいに、二礼二拍手一礼すればいいんだよね?」
先日、夫が義父のお葬式の前日にこんなことを言ってきました。
「え?神社とお葬式は違うよ」と私が答えると、「あれ?そうなん?」と困った顔。
普段神社でのお参りに慣れていると、つい同じ作法をしてしまいそうですよね。
でも、これは神式での参拝方法なんです。
仏式では拍手はNG
仏式のお葬式では、拍手(柏手)は打ちません。
私も以前、お寺で参拝したとき、危うく拍手しそうになって「ダメダメ!」と心の中で叫びました(笑)。
仏式では、胸の前で静かに手を合わせて一礼するのが基本。
両手を合わせるときは、手のひらをしっかりと合わせ、親指を軽く立てるようにすると自然に見えます。
神式の場合
神式の場合は、二礼二拍手一礼が正式な作法です。ただし、葬儀では少し違う形になることがあります。
葬儀や通夜では、拍手を省略したり、音を立てない「忍び手(しのびて)」と呼ばれる拍手をすることが多いです。
忍び手とは、両手を合わせて拍手を打つ動作をしながらも、音を立てない作法のこと。
私も友人のお父さんの神式葬儀で参列したとき、「え、拍手していいの?」と戸惑いましたが、前の方々が音を立てない忍び手をしているのを見て、慌てて真似したことがあります。
また、地域や神社によって作法が微妙に異なるため、もし不安なときは受付で確認しておくと安心です。
黙礼の基本マナー
葬儀では「黙礼」が基本とされています。
黙礼とは、声を出さずに静かに礼をすること。厳かな雰囲気の中で、余計な動作や音を立てずに故人へ気持ちを伝えるための作法です。
黙礼のやり方
-
祭壇の前に立つ
(歩くスピードも焦らずゆっくりと。私はいつも緊張して早歩きになりがちですが…) -
軽く腰を折る
(45度ほどの深めのお辞儀が望ましいです) -
そのまま1~2秒静止
(ここで気持ちを整えて、「ありがとうございました」と心の中で唱えると自然と落ち着きます) -
ゆっくり頭を上げる
私も昔は、頭だけペコペコと動かしていて、子どもに「ママ、頭だけペコペコするのは失礼だよ」と言われてハッとしたことがあります(笑)。
目線もポイント
頭を下げたときは、足元ではなく斜め前に目線を落とすと綺麗に見えます。
背中を丸めすぎず、腕は体の横に沿わせるか、女性の場合は前で軽く揃えると上品に見えますよ。
お辞儀って一見簡単そうに見えるけど、ちょっとした所作で印象が変わるもの。
「ちゃんと礼儀正しくできたかな」とあとで思い返すよりも、その場でしっかりと心を込めることが、何より大切だと感じています。
線香・焼香時の所作
線香をあげる手順
仏式葬儀でのお線香は、宗派によって細かな違いがあるものの、基本的な流れはほとんど同じです。
でも初めてのときは、「どこで一礼するの?」「火はどうやってつけるの?」と戸惑いますよね。
お線香をあげる基本的な流れ
-
祭壇の前に進み、遺族に一礼
(通路を歩いているときから姿勢を正すと落ち着きます) -
祭壇に向かって一礼
(故人へのご挨拶。「これまでありがとうございました」という気持ちを込めて) -
線香を1本取り、火をつける
火をつけた後、つい手で仰いで消したくなりますが、これはNG。
私も初めてのとき、火を消すために手でパタパタ仰いでしまい、あとで義母に「手で仰ぐのは良くないから、軽く振って消すのよ」と教わりました。 -
香炉に立てる
宗派によっては線香を寝かせる場合もあるので、もし迷ったら葬儀場スタッフに小声で聞くと安心です。 -
合掌し、一礼
(両手を合わせ、心の中で冥福を祈ります。私もここで「どうか安らかに」と必ず唱えています) -
遺族に再度一礼して下がる
線香をあげるときって、後ろに人が並んでいると焦ってしまいますよね。でも、動作を急ぎすぎると香炉に線香を落としたり、火が消えなかったりと失敗しがち。
私も以前、焦って線香を倒してしまい、慌てて立て直して恥ずかしかったことがあります…。
「ゆっくり落ち着いて」を心がけるだけで印象も全然違いますよ。
焼香の作法|宗派別ポイント
葬儀の焼香には、立礼焼香、座礼焼香、回し焼香があります。
最近の葬儀場では立ったまま行う立礼焼香が多いですが、親族席や地域によって座礼焼香、回し焼香が行われることもあります。
焼香の基本手順
-
焼香台の前に進み、遺族と祭壇に一礼
(私はここで緊張しすぎて一礼を忘れそうになるので、必ず「最初に一礼」と唱えてから進むようにしています) -
抹香を右手でつまむ
-
目の高さまで持ち上げ、額に軽く近づける(押しいただく)
これは「香を仏前に捧げる」という意味があり、気持ちを表す大切な所作です。 -
香炉に静かにくべる
-
宗派によってこれを1回~3回繰り返す
-
合掌し、一礼
-
遺族に一礼して下がる
宗派別ポイント
-
浄土真宗
押しいただかず、つまんだ香をそのまま香炉へくべる。
私の祖父のお葬式も浄土真宗で、「あれ?押しいただかなくていいの?」と戸惑いました。 -
天台宗・真言宗
3回焼香するのが一般的。 -
臨済宗・曹洞宗(禅宗系)
2回が多いです。
私も別のお葬式で、祖父と同じように押しいただかずに焼香したら、あとで母に「今日は押しいただく宗派だったよ」と言われて、冷や汗をかいたことがあります…。
でも正直、宗派まで完璧に覚えるのは大変ですよね。
そんなときは、前の人のやり方をそっと見て真似すれば大丈夫。周りの動きを見ておくと安心感が違います。
そうすれば、たとえ動作が少し違っても、きっと心は届くと私は信じています。
まとめ|礼を尽くす振る舞いを
お葬式やお通夜は、突然やってくることが多いですよね。
私も「もっと早く知っておけば良かった…」と何度思ったことか。
でも、祭壇の意味や作法、お辞儀や焼香のポイントを知っていれば、いざというときにも落ち着いて行動できます。
大切なのは、故人への感謝と遺族への配慮。
「こうしなきゃ」と肩に力を入れるよりも、心を込めてお辞儀やお焼香をする気持ちが、一番礼を尽くすことになると感じています。
ぜひ、この記事を読んだ今、家族で話し合ってみてください。
「もしものとき、どうする?」って。
知っているだけで、きっと自分も家族も救われる瞬間があると思います。