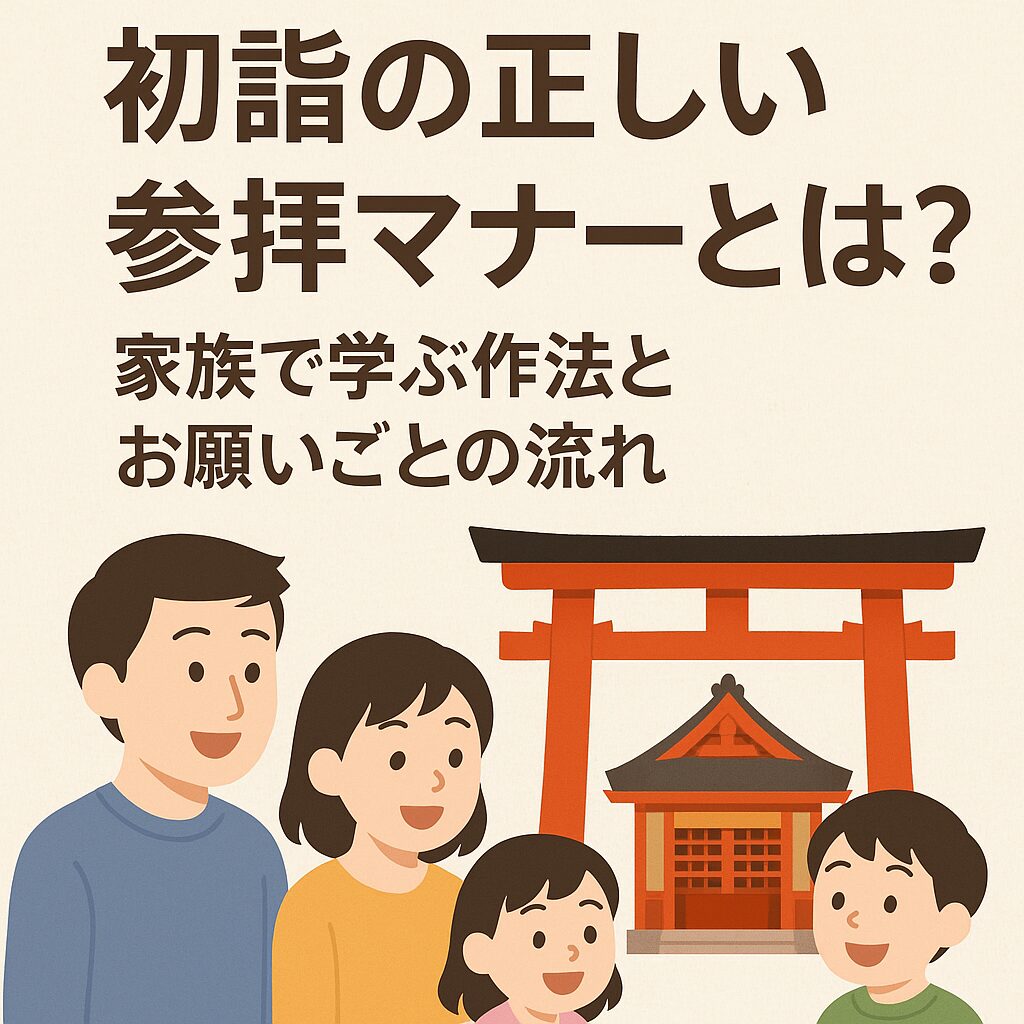新年を迎えると、「今年も初詣に行かなくちゃ」と思いますよね。でも、いざ神社やお寺へ行くと、「この作法で合ってる?」「子どもにも正しく教えたいけど自信がない…」と不安になることも。私も毎年、鳥居をくぐるときやお参りの手順で迷っていました。
今回は、そんな私が家族と一緒に調べて実践した、初詣の基本マナーと作法をまとめます。これを読めば、新年のスタートを清らかな気持ちで迎えられますよ。
初詣の意味と目的
なぜ初詣に行くのか
「初詣って、なんで行くの?」
元旦の朝、テレビを見ながらお餅を食べていた息子に突然聞かれて、私は思わず「うーん…」と考え込んでしまいました。
毎年当たり前のように家族で初詣に行っているけど、その理由を子どもにちゃんと説明したことってなかったかも…と反省。
そこで一緒に調べてみることにしました。
初詣は、その年1年の平穏無事や家族の健康、幸せを神様や仏様にお願いする行事だそうです。
昔は「年籠り(としごもり)」といって、大晦日の夜から元旦にかけて神社に泊まり込みでお祈りをしていたみたいですね。
夜通し神社で過ごすなんて、今の感覚ではちょっと想像がつかないけれど、それだけ一年の始まりを大切にしていたんだなと感じます。
最近では、元旦にこだわらず、三が日や松の内(1月7日頃まで)にお参りする家庭も多いそう。
我が家も、元旦の朝はおせちを食べてのんびりしてから、2日か3日に初詣へ行くのが恒例です。
子どもたちにとっては、お参り後に引くおみくじや、境内で食べる甘酒が楽しみのようですが(笑)、
「神様に今年もよろしくお願いしますってご挨拶するんだよ」と伝えると、「そっか!」と納得してくれました。
大切なのは、「いつ行くか」よりも、「感謝とお願いの気持ちを込めてお参りすること」だと感じています。
神社とお寺の違い
初詣に行く場所として、神社とお寺のどちらに行くか迷うことってありますよね。
私は昔、「どっちも似たようなものじゃないの?」と思っていましたが、実は意味合いが少し違うと知りました。
神社は、八百万(やおよろず)の神様が祀られていて、日本古来の神道の信仰の場。
自然や土地の神様、家族を守ってくれる氏神様などが祀られているので、私も子どもたちには「ここは〇〇神社だよ。私たちの住んでいる町を守ってくれる神様がいるんだよ」と説明しています。
一方、お寺は仏教のお寺で、仏様が祀られている場所。
初詣では、お寺で護摩焚きをしてもらったり、お札を受けたりすることもあります。
私の実家では、毎年お寺で護摩焚き供養を受ける習慣がありました。
炎の前で住職さんが読経する迫力に、子どもの頃はちょっと怖かった思い出もあります(笑)。
神社とお寺、どちらに行くかは家庭の習慣で決めてOKとのこと。
実際、住職さんも「大切なのは感謝と謙虚な気持ちを持ってお参りすること」とお話されていました。
だから我が家では、神社でお参りをしてから、お寺にも立ち寄ってお墓参りをすることもあります。
年の初めに神様にも仏様にも手を合わせると、「今年も頑張ろう」という気持ちになれるんですよね。
参拝時のマナー
鳥居のくぐり方
神社へ向かうとき、まず最初に通るのが鳥居ですよね。
私は毎回、鳥居を見上げると、「ここから神様の世界に入るんだな」という気持ちになります。
昔、祖母に「鳥居をくぐるときは一礼しなさい」と言われていましたが、当時はよくわかっていませんでした。
でも大人になってから、その意味を知ると納得。
鳥居は神様の聖域への入り口で、これからお邪魔しますという挨拶の意味があるんだそうです。
今は、私が子どもたちに同じことを伝えています。
「これから神様のお家に入るから、ご挨拶しようね」と言うと、息子も娘も素直にペコリと頭を下げてくれます。
その姿がとても可愛くて、私も自然と笑顔になります。
また、鳥居をくぐるときは真ん中を歩かず、端を歩くのがマナー。
真ん中は神様の通り道だから、と聞いたとき、「なるほど!」と思いました。
ただ、子どもはつい真ん中を駆け抜けたがるんですよね(笑)。
毎回、「こっちだよ」と手をつないで誘導しています。
そんな小さなやり取りも、初詣ならではの大切な時間だなと感じています。
手水舎での作法
境内に入るとまず目に入るのが手水舎。
冬の寒い日だと、「冷たくてやだ〜」と子どもたちは渋い顔をしますが(笑)、ここで心と体を清めることはとても大切なんですよね。
私が子どもの頃は、「とりあえず手を濡らせばいいのかな」と適当に済ませていましたが、大人になってから正しい作法を知りました。
やり方は、
-
右手で柄杓を持って左手を清める
-
左手に持ち替えて右手を清める
-
再び右手に持ち替え、左手に水を受けて口をすすぐ(柄杓に直接口をつけないよう注意)
-
もう一度左手を清める
-
最後に柄杓を立てて残った水で柄を流して戻す
一度で全部の動作を行うので、最初は私も戸惑いました。
「えーっと次はどっちの手だっけ?」と焦ったことも。
子どもたちに教えるときは、「まずは左手、次は右手、そしてお口をすすいで…」と一緒に確認しながらやっています。
息子は「まるで忍者修行みたい!」と楽しそうにやってくれました。
柄杓にはたくさん水を汲みすぎないこともポイント。
「一杯の水で全部やるんだよ」と伝えると、息子は「わかった、節水だね!」と妙に納得していました(笑)。
こうして作法を覚えていく過程も、初詣の醍醐味の一つだなと感じます。
お参りの手順
二礼二拍手一礼の流れ
いよいよ本殿でのお参りです。
ここまで来ると、背筋がピンと伸びる感じがしますよね。
でも、私も最初は「二礼二拍手一礼ってどの順番だったっけ?」と戸惑っていました。
大人になってからも、なんとなく見よう見まねでやっていた部分があったので、改めてちゃんと覚えようと思い、子どもたちにも教えるようになりました。
神社での基本は「二礼二拍手一礼」。
-
深いお辞儀(礼)を2回する
→ ここでは、腰からしっかり曲げるように子どもたちに教えています。「頭だけじゃなくて、お腹から折る感じだよ」と言うと、息子も娘も「わかった!」と真似してくれます。 -
手を胸の高さで合わせ、2回柏手(拍手)を打つ
→ パンッ、パンッと打つときも、「音を立てるのは神様への合図なんだって」と話すと、娘は「じゃあ神様、ちゃんと聞いてくれるね!」と嬉しそう。 -
そのまま手を合わせ、感謝やお願いごとをする
→ ここでは静かに目を閉じて、心の中で感謝とお願いごとを伝えます。 -
最後にもう一度深くお辞儀をする
→ 最後のお辞儀で、「ありがとうございました」の気持ちを込めると、心がすっきりします。
ちなみにお寺では拍手はせず、合掌のみです。
この違いも子どもと一緒に確認してから行くと、「知ってるよ!」と得意げにやってくれるので、ちょっとした知識クイズ感覚で盛り上がります。
去年の初詣でも、息子が「二礼二拍手一礼だよね?」と周りに聞こえる声で言っていて、周囲の人がクスッと笑っていました(笑)。
でも、子どもなりに覚えて実践している姿を見ると、教えてよかったなと思います。
お願いごとの作法
お願いごとをするとき、私はいつも「まずは感謝を伝える」ようにしています。
以前、神主さんのお話で「お願いばかりじゃなく、感謝を伝えることが大切です」と聞いてから、ずっと心がけています。
たとえば、
「去年も家族みんなが元気で過ごせました。ありがとうございます。」
「今年も家族みんなが笑顔でいられますように。」
そして最後に、もし個人的なお願いごとがあれば、「〇〇ができますように」と伝えるようにしています。
息子は、「サッカーが上手になりますように!」と必死にお願いしていました(笑)。
娘は、「プリキュアになれますように」と言っていて、可愛くて思わず笑ってしまいましたが、本人は真剣そのもの。
神社は感謝を伝える場、お寺は祈願をする場と言われることもありますが、どちらでも日々の感謝と謙虚な気持ちを持つことが大切なんだなと感じます。
お願いごとを伝えたあと、深呼吸をすると気持ちがすっと落ち着いて、「よし、今年も頑張ろう」と前向きな気持ちになれます。
まとめ|新年のスタートを清らかに
初詣は、なんとなく行くものではなく、新しい1年を感謝と共に始める大切な行事。
作法やマナーを知っておくことで、子どもにも自然と伝えていけますよね。
我が家も今年は、参拝前に「鳥居はどうするんだった?」「手水舎は?」とクイズ形式で確認しながら出かける予定です。
ちょっとした知識があるだけで、初詣がより心に残るものになるはず。
ぜひ家族みんなで、清らかな気持ちで新年をスタートさせてください。