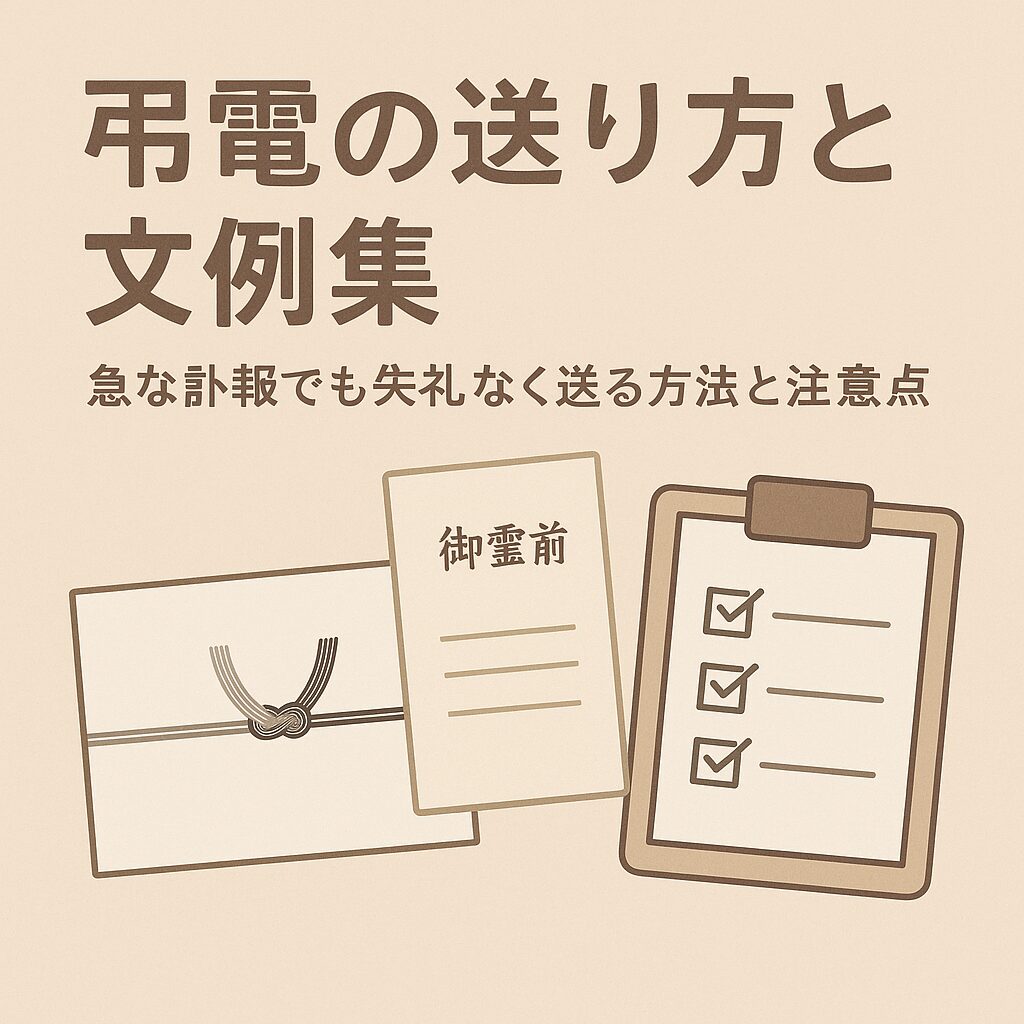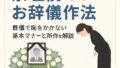「弔電って、どこで頼むの?どんな言葉を書けばいいの?」
親戚や友人のお葬式の連絡が入ったとき、私はいつも慌ててしまいます。子どもが小さいうちは参列できないことも多く、せめて弔電だけでも…と思うけれど、いざ送ろうとすると、文章もマナーも自信がなくて。
今回は、私が実際に弔電を送ったときに調べたことや感じたことをもとに、弔電の意味や送り方、選び方から、すぐ使える文例集までまとめました。
もし今、同じように悩んでいる方の助けになれば嬉しいです。
弔電とは?
弔電を送る意味とシーン
弔電とは、お葬式や通夜などで故人を偲び、遺族にお悔やみの気持ちを伝える電報のことです。
私も最初は「お葬式に電報なんて必要なのかな?」と思っていました。
電報って、結婚式のお祝いメッセージのイメージが強かったんですよね。
でも実際に親戚の葬儀で、弔電が読み上げられているのを聞いて、とても温かい気持ちになりました。
遠くに住んでいて来られなかった叔父さんからの弔電を読んでもらったとき、
「離れていても、ちゃんと見守ってくれているんだな」
と感じて、なんだか胸がじーんとしたんです。
特に、小さな子どもがいるとお葬式に参列するのも難しいですよね。
実際、私も子どもが発熱して家族全員で行けなくなったことがありました。
そのときは慌てて弔電を手配したんですが、あとから義母に
「弔電、読ませてもらったよ。気持ちが伝わって嬉しかった」
と言ってもらえて、送って良かったなと心から思いました。
弔電は、参列できないときに代わりに気持ちを届けてくれる大切な存在です。
弔電サービスの選び方
最近では、弔電もインターネットから簡単に申し込める時代になりました。
昔はNTTに電話するしかないと思っていたけど、今は選択肢が豊富で驚きます。
私が実際に使ったことがあるのは、NTTの「D-MAIL」と楽天市場で注文できる弔電サービスの二つ。
NTTの弔電(D-MAIL)
-
電話やインターネットから簡単に注文できる
-
料金は台紙なしのシンプルタイプなら1,000円台から
(台紙のデザインやお花付きにすると料金アップ) -
当日配達が可能なので、急ぎのときでも安心
楽天市場の弔電サービス
-
花や線香がセットになっている商品が多い
-
台紙のデザインが豊富で、故人や遺族の好みに合わせやすい
-
楽天ポイントが付くので、普段から楽天を使っている人にはお得感あり
ただし楽天市場の弔電は、即日配達に対応していない店舗も多い印象です。
急ぎのときは到着予定日をしっかり確認するか、NTTや郵便局のレタックスを利用する方が無難。
最近は郵便局のレタックス(ネットで送れる弔電サービス)も便利ですよ。
私の友人はレタックスで注文して、翌日の告別式に届いたそうです。
どのサービスを選ぶ?
✅ 急ぎならNTTやレタックス
✅ お花や線香も一緒に贈りたいなら楽天市場
こんなふうに、状況や予算に合わせて選ぶといいと思います。
どのサービスを選んでも、最終的には「故人を想う気持ち」が一番大切。
私は毎回、「読んでもらったときに遺族が少しでも心安らぐように」と思いながら文章を考えています。
送るタイミングと方法
通夜・葬儀のどちらに送るか
弔電を送るタイミングは、基本的に通夜か葬儀・告別式に届くように手配します。
私も以前、叔母が亡くなったときに「通夜に送るべき?葬儀に送るべき?」と悩みました。
通夜は夕方から夜にかけて行われることが多いので、当日の朝に連絡があったとしても、地域や時間帯によっては当日配達が難しいこともあります。
実際に私がそのときNTTに問い合わせたら、
「通夜には間に合わない可能性があるので、葬儀・告別式に届くよう手配するのがおすすめです」
と教えてもらいました。
通夜と葬儀、どちらがいい?
✅ 通夜に送る場合
・当日午前中までに手配が必要
・夕方〜夜開催なので、地域によっては当日配達が間に合わない
✅ 葬儀・告別式に送る場合
・午前中に行われることが多い
・前日までに手配すれば確実
・弔電を読み上げる時間が設けられることが多く、遺族に気持ちが伝わりやすい
私は結局、葬儀に届くように手配しました。
当日、弔電が読み上げられている様子を義母から聞いて、「参列できなかったけど、ちゃんと気持ちは届いたんだな」とホッとしたのを覚えています。
当日間に合わない場合の対応
「今日の午後が通夜」と急に連絡がきたとき、正直焦りますよね。
私も子どもが幼稚園から帰ってくるタイミングで訃報が入り、
「今から弔電頼める?どうしよう…」
と頭が真っ白になったことがありました。
もし当日中の配達が無理な場合は、無理に弔電を送るよりも、お悔やみの手紙と香典を郵送する方が丁寧だと葬儀社の方に教えてもらいました。
間に合わないときの対応例
✅ お悔やみの手紙を書く
簡単な便箋でも大丈夫。
「このたびはご逝去の報に接し、心よりお悔やみ申し上げます。」
といったシンプルな文章でも、遺族には十分気持ちが伝わります。
✅ 香典を現金書留で郵送する
郵便局で現金書留封筒を購入し、香典袋ごと送ります。
私もこの方法で送り、後日「忙しいのにありがとうね」と言ってもらえました。
注意点
後日弔電を送るのは避けた方がいいと言われています。
理由は、弔電はあくまで葬儀や通夜の場で読み上げるものだから。
もし間に合わなかった場合は、無理せず手紙と香典で対応するのがマナーです。
私も初めてのときは、本当に右往左往しました。
でも「気持ちを伝えたい」という思いがあれば、どんな形であれ、きっと遺族に届くと思います。
文例集(一般・会社関係)
一般向け弔電文例
ここでは、親戚や友人知人に向けた一般的な弔電文例をご紹介します。
文例① 親戚に向けて
ご逝去の報に接し、心よりお悔やみ申し上げます。
生前のお姿を偲び、ご冥福をお祈りいたします。
この文例は、叔父さんや叔母さんなど、比較的年齢が離れた親戚に送るときによく使われる表現です。
私も以前、夫の伯父が亡くなったときはこの文面を選びました。
あまり長く書こうとすると言葉選びに迷ってしまうので、短くても失礼がなく、かつ気持ちが伝わる定型文を選ぶと安心です。
文例② 友人や近しい知人へ
突然の訃報に接し、驚きと悲しみでいっぱいです。
どうか安らかにお眠りください。
こちらは、普段から親しくしていたママ友のお父様が亡くなったときに使った文例です。
最初は「ご遺族の皆様…」と書こうと思ったけれど、あまりにかしこまりすぎると距離を感じさせてしまう気がして、このようなシンプルで気持ちを直接伝える形にしました。
私が思うのは、弔電は“長さ”ではなく“気持ち”が大切だということ。
実際、義母からも「短くてもいいから、こうやって送ってくれるだけで嬉しいよ」と言ってもらえました。
会社関係向け弔電文例
上司や取引先など、仕事関係で弔電を送る場合は、一般向けよりも格式や表現に気をつける必要があります。
文例① 取引先へ
ご尊父様のご逝去の報に接し、謹んでお悔やみ申し上げます。
ご遺族の皆様におかれましては、どうぞお力落としのございませんようお祈り申し上げます。
取引先の社長や役員の親御さんが亡くなったときなど、ビジネス上で送る場合は、名前ではなく「ご尊父様」「ご母堂様」と表現します。
以前、私の夫の会社でも社長のお母様が亡くなられた際、この文例に近い形で弔電を送りました。
夫曰く「文章が失礼なく整っていて助かった」とのこと。
特に会社名義で送る場合は、こうした定型表現が安心ですね。
文例② 上司・同僚の家族へ
ご母堂様のご逝去を悼み、謹んでお悔やみ申し上げます。
ご家族の皆様のご平安を心よりお祈り申し上げます。
こちらは、同じ部署の上司や同僚のご家族が亡くなったときに使える文例です。
私も以前、会社でまとめて弔電を送る際、総務の先輩にこのような文面を教えてもらいました。
自分で考えるとつい「このたびは…」と口語表現になってしまいがちですが、会社関係では避けるのがマナーです。
会社関係で気をつけたいこと
✅ 「このたびは…」などの口語表現は使わない
✅ 「ご冥福をお祈りいたします」よりも、「謹んでお悔やみ申し上げます」を優先
✅ 送る相手との関係性(取引先・上司・同僚)に合わせて表現を変える
弔電は普段書く機会が少ないからこそ、いざというときに慌ててしまいますよね。
私も毎回、過去のメモやネットの文例集を見返しています。
NG表現と注意点
忌み言葉とは?
弔電で一番気をつけたいのが「忌み言葉」です。
忌み言葉とは、死や不幸が繰り返されることを連想させる言葉のこと。
普段の生活では何気なく使っている表現でも、お葬式の場面ではタブーになることがあります。
例えば、
-
重ね重ね
-
再び
-
追って
-
次々
など。
私も初めて弔電を送ったとき、
「重ね重ねご厚情を賜り…」
と書きそうになって、途中で気づいてゾッとしました。
この表現、普段のお礼状ではよく使いますよね。
でも弔事では「悲しみが重なる」という意味に取られてしまうことがあるそうです。
子どもにも、「同じ言葉でも場面によっては失礼になることがあるんだよ」と話したことがあります。
避けるべき表現例
具体的に、弔電で避けるべき表現にはこんなものがあります。
繰り返しや連続を連想させる言葉
-
繰り返し
-
重ね重ね
-
再び
-
またまた
-
続いて
-
次々
→ 「不幸が繰り返される」「悲しみが続く」ことを連想させるため。
繁栄や上昇を意味する言葉
-
ますます
-
昇進
-
発展
→ 慶事では良い意味ですが、弔事では「死後にますます…」と受け取られかねないため避けます。
明るすぎる表現
-
お元気で
-
頑張ってください
-
明るい未来を祈ります
→ 喪中で心が沈んでいるときに、「元気」「頑張って」という言葉は負担になることがあります。
その他注意点
弔電では「このたびは…」という口語表現も避け、
「このたびのご訃報に接し、謹んでお悔やみ申し上げます」
のように、より格式のある文章にすると安心です。
まとめ|心を込めたメッセージを
弔電は、直接会えないときでもお悔やみの気持ちを伝えられる大切な手段です。
私も実際に送ってみて感じたのは、文章の長さやきれいさよりも、「相手を想う気持ち」が一番大事だということ。
忌み言葉など最低限のマナーを守った上で、あまり難しく考えず、素直な気持ちを込めてみてください。
もし今、弔電を送るか悩んでいるなら、ぜひ今回紹介した文例を活用して、心のこもったメッセージを届けてあげてくださいね。