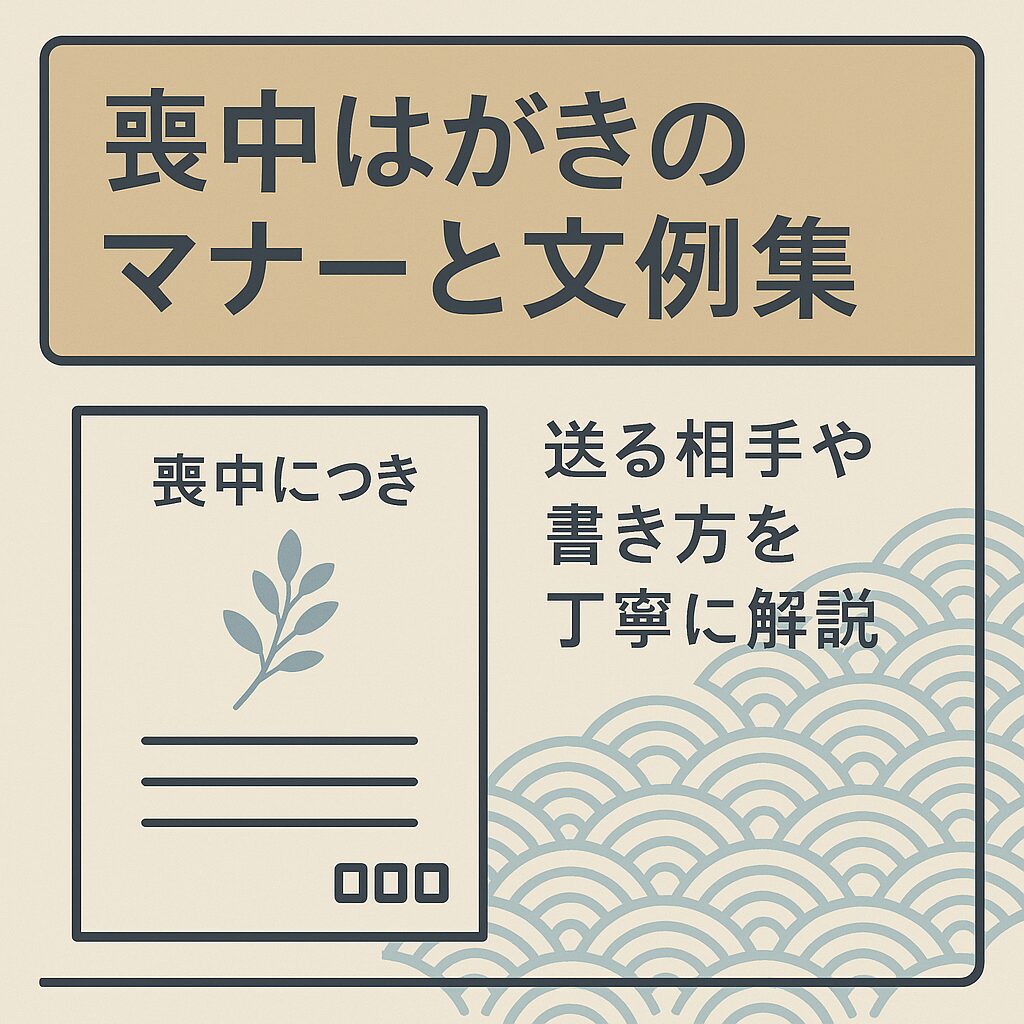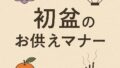身内に不幸があった年、年賀状を出さずに喪中はがきを送るのが一般的ですが、「いつ出せばいいの?」「どんな文面にすればいいの?」と迷う方も多いのではないでしょうか。
このページでは、喪中はがきの基本マナーや送る相手の範囲、タイミング、使える文例まで、初めてでも安心して準備できるよう丁寧に解説します。
大切なのは、形式よりも相手への心遣い。この記事を参考に、失礼のない喪中はがきを準備しましょう。
喪中はがきとは?
喪中はがきの意味と役割
喪中はがきとは、家族や近親者に不幸があった際に、喪に服しているため新年の挨拶を控える旨を伝えるために送る通知用のはがきです。日本の年賀状文化においては、新年の挨拶を交わすことが長年の慣習となっていますが、喪中の年はこの習わしを控えるのが一般的です。そのため、年賀状を毎年交わしている相手には、事前に喪中であることを知らせる必要があります。
この喪中はがきは単なる年始欠礼の連絡ではなく、受け取る相手への「配慮」や「気遣い」を表す大切な礼儀のひとつでもあります。突然年賀状が届かなかったり、喪中であることを知らないまま年賀状を送ってしまったりすると、相手に気まずい思いをさせる可能性もあるため、事前の喪中はがきは円滑な人間関係の維持にもつながります。
なお、喪中はがきに宗教的な意味合いはなく、仏教・神道・キリスト教など、宗教に関係なく広く用いられています。また、喪中の定義や形式には厳密な決まりはなく、地域や家庭の考え方によって対応も異なりますが、一般的には故人を偲ぶ期間として、新年の祝賀を控えることが礼儀とされています。
喪中はがきを出す際は、堅苦しすぎない程度にフォーマルな文面を心がけ、「新年のご挨拶をご遠慮させていただきます」といった表現を中心に、故人が亡くなったことと喪中であることを簡潔に伝えるようにしましょう。
送る相手と送らない相手
喪中はがきを送る対象として基本となるのは、「毎年年賀状のやりとりをしている相手」です。とくに、長年の友人や親戚、職場の上司・同僚、地域の知人など、年賀状による交流が習慣となっている方々には、必ず送るようにしましょう。
一方で、すべての人に喪中はがきを出す必要があるわけではありません。以下のようなケースでは、喪中はがきを省略することもマナー違反にはなりません。
- もともと年賀状のやりとりがない相手(久しく交流がない人など)
- 家族など、喪中であることをすでに直接伝えている相手(電話やメール、対面など)
- 形式的な付き合いでの年賀状交換(会社の部署や営業所、名刺交換しただけの関係など)
ただし、仕事関係でも個人的な交流がある場合や、相手から気遣いをいただくような関係性であれば、喪中はがきを出しておくことで丁寧な印象を与えることができます。
また、自分が喪中であっても、相手から年賀状を受け取る可能性はあります。そのような場合には、年が明けてから「寒中見舞い」という形で返礼をするのがマナーです。寒中見舞いには、年賀状へのお礼とともに、喪中だったため年始のご挨拶ができなかったことを簡潔に伝えましょう。これにより、相手への感謝と配慮をきちんと示すことができます。
喪中はがきを出すことは、形式的な行為に見えるかもしれませんが、実際には「相手を思いやる気持ち」を形にしたものです。相手との関係性や状況を踏まえながら、心を込めて対応することが大切です。
出すタイミング
喪中はがきを出す時期
喪中はがきを出すタイミングは非常に重要で、受け取る相手に配慮を示すためにも、年賀状の準備が始まる前に届けることが基本です。一般的には、11月中旬から12月初旬に届くように送るのが理想とされています。これにより、相手が年賀状の宛名書きや印刷に取りかかる前に、喪中の事情を知ることができ、誤って年賀状を送ってしまうといった事態を避けることができます。
具体的には、遅くとも12月10日頃までに相手の手元に届くようにしましょう。郵便事情を考慮すると、11月20日〜30日頃までに投函するのが安心です。とくに12月に入ると年賀状の準備が本格化するため、11月中に準備と発送を済ませておくことが、もっとも丁寧な対応といえます。
なお、喪中はがきは印刷会社や郵便局などで作成・印刷を依頼する場合、混雑する年末には納期がかかることもあります。早めに原稿を用意し、11月初旬には発注しておくと安心です。
一方で、故人が11月下旬や12月に亡くなった場合、どうしても喪中はがきを送ることが間に合わないケースもあります。そのような場合は、無理に遅れて喪中はがきを出すのではなく、以下のように寒中見舞いでの対応に切り替えましょう。
間に合わなかった場合の対応
12月中旬〜下旬、あるいは年末に不幸があった場合、喪中はがきを出すタイミングが過ぎてしまうことがあります。この場合、年明け以降に「寒中見舞い」として、改めて相手に事情を伝えるのが適切なマナーです。
寒中見舞いの送付時期は、1月7日(松の内が明けた日)〜2月初旬までが一般的とされています。寒中見舞いはもともと季節の挨拶状として使われていましたが、近年では喪中で年賀状を控えた方が年始のご挨拶代わりに送るケースも増えています。
寒中見舞いの文面では、以下のようなポイントを押さえておくと丁寧な印象になります。
- 年賀状をいただいたことへの感謝
- 喪中であったため、新年のご挨拶を控えた事情
- 故人が亡くなったこと(簡潔で構わない)
- 相手の健康や安寧を祈る言葉
例文:
寒中お見舞い申し上げます
ご丁寧な年賀状をいただきありがとうございました
実は昨年〇月に〇〇(続柄)が永眠いたしまして
年始のご挨拶を控えさせていただきました
本年も変わらぬご厚誼を賜りますようお願い申し上げますこのように、寒中見舞いは喪中はがきが間に合わなかった場合の補足的な役割を果たすだけでなく、年始の気持ちを伝える大切な手段でもあります。受け取った相手にも丁寧で配慮のある印象を与えることができますので、状況に応じて上手に活用しましょう。
文例集|シンプル・丁寧な例
喪中はがきの文面は、基本的にフォーマルで落ち着いた表現が求められます。ここでは、誰にでも使える一般的な文例と、親しい人向けに少し柔らかい表現を用いた例文を紹介します。シチュエーションに応じて、適切な表現を選びましょう。
一般的な例文
喪中につき年始のご挨拶を失礼させていただきます。
去る〇月に〇〇(続柄)が永眠いたしました。
本年中に賜りましたご厚情に深く感謝申し上げます。
明年も変わらぬご交誼のほどお願い申し上げます。このような文面は、フォーマルで誰にでも使える基本形です。親戚や知人、職場関係など、あらゆる相手に対応できる内容になっています。簡潔で丁寧な表現を心がけると、より印象が良くなります。
文章の中に具体的な続柄(父、母、祖父、祖母など)を記載することで、相手にも状況が伝わりやすくなります。また、句読点の使用は自由ですが、句点(。)を省くのが慣例とされる場合もあります。
親しい人向けの例文
ご無沙汰しております。
私事で恐縮ですが、〇月に〇〇が他界いたしました。
本年は喪中につき、新年のご挨拶を控えさせていただきます。
どうか穏やかな新年を迎えられますようお祈り申し上げます。親しい友人や昔からの知人など、日常的に交流のある相手には、やや柔らかい表現を取り入れることで、より温かみのある印象を与えることができます。冒頭で近況に触れるなど、相手との関係性に応じたアレンジも可能です。
カジュアル寄りな例文(友人向け)
今年は喪中につき、新年のご挨拶を控えさせていただきます。
〇月に身内が他界し、静かに年末年始を過ごす予定です。
昨年中はお世話になり、本当にありがとうございました。
本年も変わらぬお付き合いをよろしくお願いします。特に気のおけない友人などには、少し口語調に近い文体を用いることで、固すぎない印象になります。ただし、礼儀は忘れず、敬意を込めた表現にすることが大切です。
文例を使用する際の注意点
- 故人の名前を記載する必要はありません(記載しても問題はありませんが、控えるのが一般的)
- 年号や命日の詳細を入れる場合は、宗教や地域の習慣を踏まえて判断する
- 複数の人と連名で出す場合は、家族全員の名前を記載する
喪中はがきの文例は、テンプレートをベースにしつつも、相手との関係や自分の気持ちに合わせて調整することがポイントです。心を込めて丁寧に言葉を選びましょう。
文例集|シンプル・丁寧な例
喪中はがきの文面は、基本的にフォーマルで落ち着いた表現が求められます。ここでは、誰にでも使える一般的な文例と、親しい人向けに少し柔らかい表現を用いた例文を紹介します。シチュエーションに応じて、適切な表現を選びましょう。
一般的な例文
喪中につき年始のご挨拶を失礼させていただきます。
去る〇月に〇〇(続柄)が永眠いたしました。
本年中に賜りましたご厚情に深く感謝申し上げます。
明年も変わらぬご交誼のほどお願い申し上げます。このような文面は、フォーマルで誰にでも使える基本形です。親戚や知人、職場関係など、あらゆる相手に対応できる内容になっています。簡潔で丁寧な表現を心がけると、より印象が良くなります。
文章の中に具体的な続柄(父、母、祖父、祖母など)を記載することで、相手にも状況が伝わりやすくなります。また、句読点の使用は自由ですが、句点(。)を省くのが慣例とされる場合もあります。
親しい人向けの例文
ご無沙汰しております。
私事で恐縮ですが、〇月に〇〇が他界いたしました。
本年は喪中につき、新年のご挨拶を控えさせていただきます。
どうか穏やかな新年を迎えられますようお祈り申し上げます。親しい友人や昔からの知人など、日常的に交流のある相手には、やや柔らかい表現を取り入れることで、より温かみのある印象を与えることができます。冒頭で近況に触れるなど、相手との関係性に応じたアレンジも可能です。
カジュアル寄りな例文(友人向け)
今年は喪中につき、新年のご挨拶を控えさせていただきます。
〇月に身内が他界し、静かに年末年始を過ごす予定です。
昨年中はお世話になり、本当にありがとうございました。
本年も変わらぬお付き合いをよろしくお願いします。特に気のおけない友人などには、少し口語調に近い文体を用いることで、固すぎない印象になります。ただし、礼儀は忘れず、敬意を込めた表現にすることが大切です。
文例を使用する際の注意点
- 故人の名前を記載する必要はありません(記載しても問題はありませんが、控えるのが一般的)
- 年号や命日の詳細を入れる場合は、宗教や地域の習慣を踏まえて判断する
- 複数の人と連名で出す場合は、家族全員の名前を記載する
喪中はがきの文例は、テンプレートをベースにしつつも、相手との関係や自分の気持ちに合わせて調整することがポイントです。心を込めて丁寧に言葉を選びましょう。
出し方の注意点
喪中はがきを送る際は、形式や見た目にも気を配ることで、相手に対する丁寧さや心遣いが伝わります。以下に、出し方のマナーや細かな注意点を解説します。
封筒は必要?ハガキだけでOK?
一般的に喪中はがきは、官製はがきまたは私製はがきを使用して送り、封筒に入れる必要はありません。はがき1枚で完結する形式が基本とされており、特別な装飾や派手なデザインは避け、シンプルな白黒ベースのデザインが主流です。
ただし、以下のようなケースでは、封筒に入れて送ることも検討されます:
- 会社や取引先など、ビジネス上で特に丁寧な印象を与えたい場合
- 私製はがきで薄手の紙を使用しており、破損や汚れが心配な場合
- 個人的に改まった形式を好む相手に送る場合
このような場合は、白無地の封筒を使用し、宛名も丁寧に書くと好印象です。また、私製はがきを使う場合は、弔事用切手(落ち着いた色味のもの)を選ぶことで、より礼儀正しく丁寧な印象を与えられます。
表書き・住所記載のマナー
宛名や差出人情報の記載には、次のようなマナーがあります。
- 宛名は縦書きが基本(ただし、横書きでも失礼にはあたりません)
- 故人の名前は記載しない(喪中はがきは差出人本人からの通知とする)
- 差出人の名前と住所は明確に記載(マンション名・部屋番号も省略せず)
- 薄墨を使う必要はない(喪中はがきはお悔やみではなく通知のため)
差出人を家族連名で記載する場合は、年齢順や続柄の順に並べるのが一般的です。
また、印刷で宛名や文面を作成することも増えていますが、手書きで丁寧に書くことで、より心のこもった印象を与えることができます。プリンターを使う場合でも、差出人の名前部分だけは手書きにするなどの工夫もおすすめです。
喪中はがきは形式やデザインだけでなく、相手に対する「心遣い」を表すもの。細かな部分にも配慮することで、より誠実な印象を残すことができるでしょう。
よくある疑問Q&A
喪中はがきに関しては、初めて準備する方や久しぶりに出す方にとって、細かな点で迷うことが多いものです。ここでは、特によく聞かれる疑問について詳しくお答えします。
Q. 喪中はがきは自分で作成してもよい?
はい、まったく問題ありません。近年は、市販のテンプレートを使用したり、PCやスマートフォンのアプリで手軽に自作する方も増えています。特にネット印刷サービスでは、デザインの選択から文面の編集、宛名印刷まで一括で行えるため、時間がない方にも便利です。
自作する場合は、文面の敬語や表現に注意し、落ち着いたデザインを選ぶよう心がけましょう。また、白黒の控えめな色合いが基本とされているため、カラーや派手な装飾は避けるのが無難です。
手書きにこだわる必要はありませんが、「自分の言葉で伝えたい」という気持ちがある場合は、文章だけでも手書きにすると、より誠意が伝わることもあります。
Q. 喪中の範囲はどこまで?
喪中はがきを出す対象としての「喪中の範囲」は、一般的には二親等以内とされています。具体的には、以下のような続柄が該当します:
- 父母
- 配偶者
- 子
- 兄弟姉妹
- 祖父母
- 孫
ただし、現在ではこの基準にとらわれず、個人の気持ちや関係性を重視して柔軟に判断する傾向が強まっています。たとえば、三親等の叔父や叔母であっても、深いつながりがあった場合には喪中として対応する方も少なくありません。
逆に、形式的なつながりにとどまる場合は、喪中はがきを出さないという選択も尊重されています。最終的には、「新年を祝う気持ちになれないかどうか」を基準に、無理のない範囲で判断することが大切です。
Q. 喪中でも年賀状を出してよい場合はある?
基本的には、喪中の年は年賀状を控えるのが一般的なマナーとされています。特に、故人との関係が深い場合や、自身が喪に服していることを大切にしたいと考えている場合は、新年の挨拶そのものを遠慮するのが望ましいです。
ただし、宗教的な考え方や地域の風習によっては例外もあります。たとえば、キリスト教では死を穢れとは捉えないため、喪中でも年賀状を出す文化がある場合もあります。また、故人の遺志によって「いつも通り過ごしてほしい」とされているケースもあります。
どうしても年始の挨拶を伝えたい場合は、年賀状の代わりに寒中見舞いや個別の手紙として丁寧に気持ちを伝えるとよいでしょう。その際は、「喪中につき年始のご挨拶を控えましたが、本年もどうぞよろしくお願いいたします」など、心を配った表現を添えるとより好印象です。
まとめ|心を込めた喪中はがきで丁寧にご挨拶を
喪中はがきは、新年のご挨拶を控える旨を伝えるだけでなく、故人を偲びながら相手への気遣いを表す大切な手段です。送る相手の選び方や出す時期、文例の使い方に少し注意を払うことで、失礼のない印象を与えることができます。
この記事で紹介したマナーや文例を参考に、形式にとらわれすぎず、自分らしい丁寧なご挨拶を心がけましょう。
心を込めた喪中はがきが、故人を想う気持ちとともに、相手の心にもきっと届くはずです。