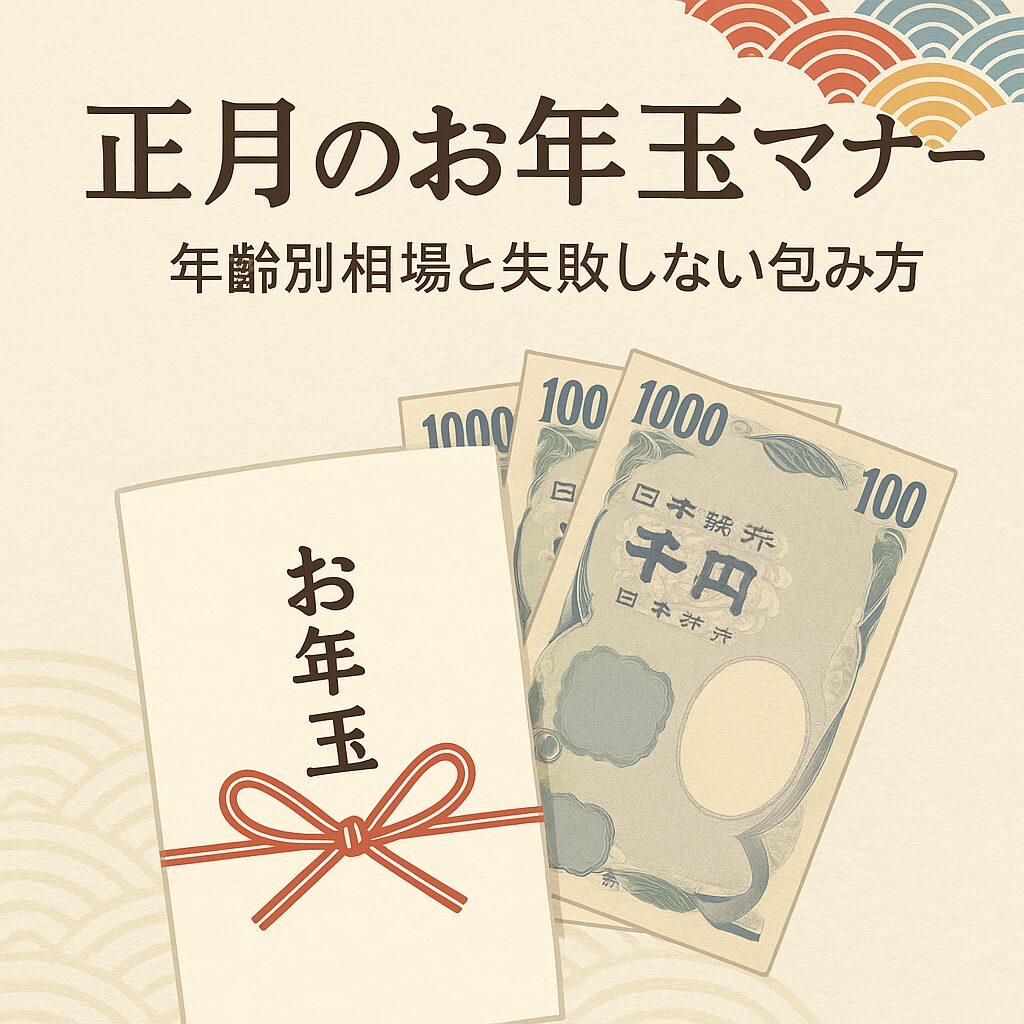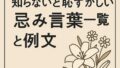お正月が近づくと、気になるのがお年玉。私も毎年、「いくら包めばいいんだろう?」「ポチ袋ってどれがいいの?」と悩みます。親戚同士で金額に差があったり、マナーを知らずに恥をかいたらどうしようと不安になることも。
今回は、そんなお年玉の意味や金額相場、渡し方のマナーまで、私自身の体験も交えてまとめました。今年のお正月は、自信を持ってお年玉を渡せますように。
お年玉の意味と由来
お年玉の起源
「お年玉ってそもそも何?」と子どもに聞かれて、答えに詰まったことがあります。
私も小さい頃は、お年玉は「お正月にもらえるお小遣い」くらいにしか思っていませんでした。でも調べてみると、実はとてもありがたい意味が込められていることを知って、驚いたんです。
お年玉の起源は、もともと神様へのお供え物だったそうです。お正月には、年神様(としがみさま)という、その年の豊作や家族の健康を司る神様をお迎えします。その年神様にお供えした鏡餅を下げて、家族に分け与えることで、神様からの力や恩恵を授かると考えられていました。
このとき分けられたお餅が「年玉」と呼ばれたのが始まり。つまり、「お年玉」とは神様からのお下がりをいただく、ありがたい贈り物だったんですね。昔はお餅やお米などの食べ物を配っていたそうです。
私がこの話を子どもにしたら、「えー!じゃあお餅くれたらいいのに」なんて言っていました(笑)。確かに、お金よりもお餅の方が神様っぽい感じがしますよね。
現代におけるお年玉の役割
時代が進み、現代ではお年玉はお金を包む形になりました。経済が発展して、物からお金へと変わったんですね。
今ではお年玉は、子どもたちにとって楽しみな「お正月のお小遣い」という感覚。うちの子も、お正月が近づくとソワソワして、「あと何日でお年玉?」なんて聞いてきます。
でも、本来のお年玉には、「新しい年を健やかに過ごせますように」という願いが込められています。お金をあげるだけでなく、その子の成長や幸せを願う気持ちを贈るものなんですね。
私は毎年、渡すときに「今年も元気に頑張ってね」と一言添えるようにしています。子どもが「うん!」と笑顔で返してくれると、こちらもほっこり。
そういえば去年は、お年玉を渡した後に「何買うの?」と聞いたら、「えっとね、全部貯金する!」と真剣な顔で言われました。お金の使い道も大事だけど、まずは無事に一年過ごしてくれることが何よりだなぁと感じました。
お年玉は、金額の大きさではなく、そこに込められた「気持ち」が一番大切なんだと思います。
お年玉の金額相場
年齢別目安
さて、一番気になるのが金額相場ですよね。私も毎年ネットで「お年玉 相場」と検索しては、あちこちの記事を見比べています(笑)。金額って地域や家庭によって差があるからこそ、「うちだけ変じゃないかな…」と不安になるんですよね。
ここで、一般的な目安をまとめておきます。
未就学児(0~5歳):500円〜1,000円
我が家は500円玉をポチ袋に入れて渡しています。まだお金の価値がわからない年齢なので、気持ち程度で十分。
うちの息子も、幼稚園の頃はもらったお年玉を全部おもちゃ箱に入れていました(笑)。「どうするの?」って聞いたら、「お金はここに入れるといいんでしょ!」と得意げ。お金=貯金箱ではなく、お金=おもちゃ箱だったようです。
小学校低学年(6~8歳):1,000円〜2,000円
この頃になると、お金の概念も少しずつ分かってきます。うちは1,000円にしていますが、夫の実家では2,000円が定番のようで、「え、倍?!」と最初びっくりしました。
ちなみに、親戚同士で金額差があると、子どもはしっかり覚えています…。以前、甥っ子が「〇〇おじさんは2,000円だったよ!」と無邪気に言っていて、場が微妙な空気に(笑)。金額設定は親戚内で話し合えると安心です。
小学校高学年(9~12歳):2,000円〜3,000円
「お年玉でゲームソフト買いたい」と言い出すころ。欲しい物の値段もわかってくるので、1,000円だと「足りない…」とションボリされることも。
我が家では、兄弟で金額に差をつけないよう同じ額にしています。ただ、上の子は「もう少し欲しいな…」と思っているかもしれませんね。難しいところです。
中学生(13~15歳):3,000円〜5,000円
ここから一気に金額が上がりますね。私の甥っ子も、もらったお年玉で部活用品やスニーカーを買っていました。
中学生になると、親戚付き合いの場でも「大人の会話」に混ざりたがるお年頃。そんな姿を見ると、「もうこんなに大きくなったんだなぁ」と感慨深いです。
高校生(16~18歳):5,000円〜10,000円
高校生になると、周囲も5,000円以上を渡す家庭が増えてきます。うちは5,000円にしていますが、夫側の親戚は1万円を包むことも。
大学生になると、「お年玉は卒業」という家庭も多いですが、我が家は20歳まで渡しています。去年、19歳の姪っ子に渡したら、「え、まだくれるの?」と嬉しそうにしていました。大人になっても、お年玉をもらうとなんだか特別感がありますよね。
渡す相手別の違い
お年玉は基本的に親戚や孫、親しい友人の子どもに渡しますが、相手との関係性でも金額感が変わります。
例えば、
-
実子・孫:相場の上限まで渡す家庭が多い
祖父母から孫へは、お小遣いとは別にお年玉を渡すところもあり、「そんなにもらって大丈夫…?」と親としては心配になることも(笑)。 -
甥・姪:相場の中央値
私も甥姪には、毎年「去年いくらだったかな?」とメモを見返して決めています。金額を上げるときは、他の親戚との兼ね合いも考えて。 -
友人の子ども:気持ち程度(500円~1,000円)
友達家族との集まりで、うちの子がもらったときは、お返しとして同じくらい渡しました。あくまで「お年玉文化を楽しむ」くらいの金額で十分ですね。
お年玉は、金額も大切だけど、やっぱり「今年も元気でいてね」という気持ちを伝える機会。金額に縛られすぎず、無理のない範囲で渡せるといいですね。
お年玉袋(ポチ袋)のマナー
選び方と書き方
お年玉袋選びって、意外と悩むところですよね。お店に行くと、キャラクター柄から和風のものまでずらりと並んでいて、「どれが正解なんだろう…」と毎年考えてしまいます。
私は最初、可愛いキャラクター柄を選んでいたんですが、義母から「お正月だから、もっときちんとしたものの方がいいんじゃない?」と言われたことがありました。
もちろん、渡す相手の年齢や家庭の雰囲気にもよると思います。一般的には、
-
未就学児~小学生:キャラクター柄でもOK
アンパンマンやすみっコぐらし、ポケモンなど、好きなキャラの袋を渡すと、「わあ、可愛い!」と大喜びしてくれます。我が家では、袋を選ぶ時から子どもと一緒に買いに行くことも。レジで「これがお年玉袋だよ」と見せると、嬉しそうにしていました。 -
中高生:シンプルな和柄や金封タイプが無難
大きくなるとキャラ袋は少し子どもっぽく感じるようで、甥っ子にスヌーピー柄を渡したら、ちょっと気恥ずかしそうに「ありがとう…」と言われたことがあります(笑)。それ以来、シンプルな市松模様や竹柄の落ち着いたものを選ぶようにしています。
表書きは「お年玉」と書き、下に自分の名前をフルネームで書くのが基本。子ども同士で袋を比べるとき、「誰からもらったか」がすぐわかるので便利です。
そういえば去年は、ディズニープリンセスの袋を選んだら、姪っ子が「この袋、宝物にする!」と言ってくれました。中身のお金より袋を大事にしていて、微笑ましかったです。
のしの有無は?
お年玉袋には、あらかじめ水引(紅白の飾り紐)が印刷されているものが多いので、改めてのしを貼る必要はありません。
ただ、正式なお年玉袋を選ぶ場合は、紅白の蝶結びが一般的。蝶結びは「何度あってもよいお祝いごと」に使う結び方なので、お正月や誕生日にはぴったりです。
逆に、結び切りの水引は婚礼や快気祝い、弔事に使われるもので、お年玉には不向きなので注意してくださいね。私も一度間違えて結び切りのポチ袋を買いそうになり、慌てて棚に戻したことがあります。
ポチ袋は、中身のお金以上に「新年を迎える特別感」を演出するアイテム。子どもが袋を開ける瞬間のキラキラした表情を見ると、「今年も渡せてよかったな」と嬉しくなります。
渡すときのマナー
手渡し時の一言
お年玉を渡すときって、ちょっと緊張しませんか?私も最初の頃は、「どう言って渡せばいいんだろう…」と悩んでいました。
「はい、これお年玉」とだけ言って渡すよりも、一言添えるとぐっと温かみが増します。
私がよく使うのは、
-
「今年も元気いっぱい過ごしてね」
小さい子には、笑顔でこう言うと「うん!」と元気に返事してくれるので可愛いです。 -
「勉強頑張ってね」
小学生以上になると、この言葉にちょっと背筋を伸ばす子も。甥っ子に言ったら、「うん…頑張る…」と少しプレッシャーになったのか、微妙な顔をしていました(笑)。言い方も優しく柔らかくが大事ですね。 -
「お母さんのお手伝いしてあげてね」
この一言は特に、親御さんが喜びます。「そうだよ、手伝ってよー」とママに言われて、子どもが照れ笑いしているのを見てほっこり。
去年は、お年玉を渡すときに「この一年、怪我しないようにね」と言ったら、「え、怪我すると思ってるの?」と真顔で返されてしまいました…。言葉選びって難しいですね(笑)。
でも、こうして一言添えることで、お金だけではない「気持ち」が伝わる気がしています。
両親・祖父母間での注意点
お年玉を渡すとき、もうひとつ気をつけたいのが両親・祖父母間の金額感覚の違いです。
家庭によっては、
-
祖父母からは渡すけど、親からはなし
「お正月は祖父母の役目」と考える家庭もあれば、 -
親も祖父母も渡す
というところもあります。
うちは両親・祖父母で金額を揃えるようにしていますが、先に相談しておかないと「えっそんなに?」と焦ることもあります。
特に義実家では、毎年金額の感覚が違うので、夫と打ち合わせ必須です(笑)。
以前、義父が孫全員に1万円ずつ渡していて、私たちも同じように包まなきゃ…?と冷や汗をかきました。でも夫に「いやいや、じいじはじいじ、うちはうちでいいよ」と言われてホッとしたことがあります。
また、お年玉は「お返し不要」とされていますが、祖父母から高額をもらったときは、お正月の帰省土産を少し奮発したり、後日子どもからお礼の手紙を送るようにしています。
金額よりも、「ありがとう」の気持ちをちゃんと伝えることが、一番のマナーかもしれませんね。
まとめ|心を込めた新年の贈り物
お年玉は、ただのお金ではなく、「今年も元気に過ごしてね」という気持ちを形にした贈り物。私も毎年悩みながらですが、渡すときの子どもたちの笑顔を見ると、「あぁ、渡せてよかったな」と思います。
今年のお正月は、ポチ袋選びも楽しみながら、気持ちを込めたお年玉を渡してみてくださいね。